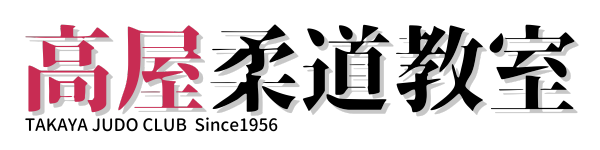柔道を習っている人やその関係者にとって、「月次試合(つきなみしあい)」という言葉はなじみのあるものかもしれません。でも、柔道をやっていない人にとっては、あまり聞いたことのない言葉かもしれませんね。
月次試合は、ただの勝ち負けを競う試合ではありません。柔道が「道」として人を育てるために、大切な役割を果たしてきた伝統ある行事です。今回は、月次試合のはじまりや目的、今のやり方、ほかのスポーツとの違いなどについて、わかりやすく紹介していきます。
月次試合のはじまりと歴史
月次試合の始まりは、柔道を作った嘉納治五郎(かのうじごろう)先生が1882年に講道館という道場をつくったころにさかのぼります。
嘉納先生は、柔道を勝つための技だけではなく、人としての成長も大事にしました。そのためには、練習だけでなく、本番のような試合を定期的に行うことが必要だと考えたのです。
そして、1884年ごろから講道館では「月次試合」という毎月の定例試合が始まりました。これは後に「紅白試合」と並んで、柔道の伝統的な試合として定着しました。戦後もこの仕組みは引き継がれ、全国の道場や学校にも広がっていきました。
月次試合の目的って?
月次試合には、主に3つの大切な目的があります。
- 自分の実力を試すため
毎日の練習だけでは、自分がどれだけ上達したのか分かりにくいですよね。月次試合では、実際の試合で自分の技を試すことができるので、成長を確認するチャンスになります。 - 昇級や昇段のための評価になる
月次試合の成績は、柔道の級や段を上げるための大切な材料になります。がんばった分だけ評価される仕組みなので、やる気につながります。 - いろんな相手と交流できる
同じ道場だけじゃなく、外部の柔道家と戦うことで、自分の技をもっと広い場で試すことができます。新しい気づきがあったり、他の人の良いところを学んだりもできます。
今の月次試合ってどんな感じ?
今も講道館では、無段者・有段者・少年部に分かれて、年に9回の月次試合が開かれています(1月と紅白試合の月は除きます)。
試合のルールは「高点試合」といって、勝ち抜き方式です。引き分けのときは、後から出てきた方が次の試合に残ります。少し特別なルールですね。
さらに、6月と10月には「紅白試合」があり、ここでとくに良い成績を出すと、その場で昇段が認められることもあります。これを「抜群昇段」といいます。
講道館だけでなく、日本全国の道場や学校でもこの仕組みを取り入れていて、地域ごとに月次試合が定期的に行われています。
他のスポーツとくらべてみよう
月次試合のように、毎月のように行われる定例の試合や大会は、柔道だけではありません。
たとえばゴルフでは「月例杯」、卓球やテニスでは「月例大会」、アーチェリーでは「記録会」、マラソンやサイクリングでは「月例走」などがあります。
これらの行事も、参加する人の技術アップややる気の維持、友だちづくりのきっかけになります。たとえば、テニスではポイントをためて特典と交換できたり、ゴルフではハンディキャップ制度で実力に合った試合ができるように工夫されています。
でも、柔道の月次試合はちょっと特別です。なぜなら、昇段や昇級という公式な評価に直結しているからです。柔道は、ただ勝つためのスポーツではなく、「人としてどうあるべきか」を大切にする武道なので、こうした制度がしっかりと結びついているんですね。
月次試合が持つ社会的な意味
月次試合は、柔道を通して人を育てる場所でもあります。年齢や体の大きさが違う人たちが、礼儀を大切にしながら試合をすることで、思いやりや協力の心が自然と身についていきます。
また、地域の道場では、保護者や地域の人たちが見守る中で子どもたちが試合に出場することが多く、地域のつながりを深めるきっかけにもなっています。これは柔道だけでなく、スポーツを通じて地域社会を元気にする取り組みとしても注目されています。
未来へ続く柔道の伝統
月次試合は、「継続」「努力」「礼儀」といった柔道の大切な考え方を、目に見える形で伝えていく行事です。これからも、その役割はとても大事になっていくと思います。
とはいえ、柔道の世界でも、指導者の数が減ったり、道場の建物が古くなったりといった問題が出てきています。だからこそ、新しい工夫が必要です。
たとえば、オンラインで審判をする仕組みを使ったり、VRを活用したり、地域のシニア世代がボランティアとして関わったりといった、新しいアイデアが少しずつ広がっています。
最後に
月次試合は、柔道が「人を育てる道」であることをあらわす、大切な伝統です。昔から続くこの試合を通して、多くの柔道家が自分を成長させてきました。
そして、月次試合で学んだことは、道場の外に出ても、人として大切な力になります。だからこそ、柔道を学ぶすべての人がこの伝統を大切にし、次の世代へ伝えていくことが大切なのです。