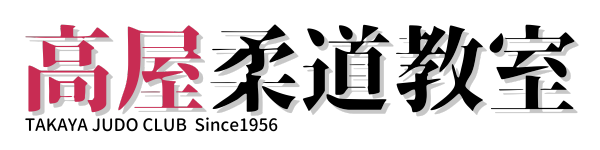〜新ルールに対応!礼儀とルールを楽しく学ぼう〜
柔道は、日本が世界に誇る武道であり、今も多くの子どもたちに親しまれています。その最大の魅力は、「礼に始まり礼に終わる」精神。礼儀を重んじながら、心と体の両方を鍛えられる点が、多くの保護者からも支持されています。
2025年からは、より安全でわかりやすい柔道を目指してルールが一部改正されました。本記事では、改正点も含めて柔道の基本とマナーを紹介します。
柔道の精神:「礼に始まり、礼に終わる」
柔道では、稽古や試合の前後に必ず「礼」を行います。これは、相手への敬意や感謝の気持ちを表すもので、柔道の精神性の中核をなしています。子どもたちはこの習慣を通じて、自然と「他人を思いやる心」を身につけていきます。
柔道の基本ルールを知ろう(2025年改正対応)
試合時間
年齢によって試合時間が異なります。
- 小学生:2分
- 中学生:3分
- 高校生以上:4分
勝敗の決まり方(3段階評価に!)
2025年から「有効」ポイントが復活しました。これにより、技の評価が以下の3段階になりました:
| スコア名 | 内容 |
|---|---|
| 一本 | 試合が即終了する完全な技 |
| 技あり | 一本に近い評価。2回で「合わせ技一本」になる |
| 有効 | 軽度な成功。尻もちや横に倒れたとき等に与えられる(新設) |
抑え込みでも時間に応じて評価が変わります:
- 5秒 → 有効
- 10秒 → 技あり
- 20秒 → 一本
禁止されている行為(中学生以下対象)
中学生以下の試合では、安全を最優先に考えた特別ルール(少年大会特別規程)が適用されます。以下のような行為は「指導」または「反則負け」となるため注意しましょう。
- 首をしめる「絞技」や、関節を極める「関節技」
- 相手を後ろ方向に強くねじる「逆背負投(韓国背負い)」
- 両ひざを同時に畳について投げる技
- 首を抱えて大外刈や払腰をする技
- 両袖を持っての技(袖釣込腰・大外刈など)
- 組手の際に、相手の袖や裾の中に指を入れる
※これらは国際ルールで認められるものもありますが、中学生以下の試合では禁止です。
礼儀作法が子どもを育てる
柔道では「強くなること」以上に、「礼儀を身につけること」が大切にされています。
道場での挨拶、試合前後の礼、仲間や指導者への敬意など、日常にも通じるマナーが柔道には詰まっています。こうした行動の積み重ねが、社会性や思いやりを育てます。
教室での成長事例(高屋柔道教室より)
高屋柔道教室では、柔道を通して多くの子どもたちが成長しています。
例えば、最初は恥ずかしがっていた子が、稽古を通じて自分から元気よく挨拶できるようになったり、試合を通じて「勝ち負け」ではなく「挑戦する勇気」を学んだりする姿が見られます。
アメブロでは、教室の活動や子どもたちの様子を紹介しています。ぜひチェックしてみてください!
柔道を通して育まれる“生きる力”
柔道はスポーツであると同時に、心を育てる道でもあります。ルールや礼儀を守る中で、子どもたちは以下のような力を身につけていきます:
- 相手を思いやる心
- 自分をコントロールする力
- あきらめない気持ち
- 負けても立ち上がる勇気
高屋柔道教室では、子どもたちが楽しみながら「心と体の両方」を育てられる環境を提供しています。興味のある方は、ぜひ見学や体験にお越しください!